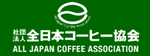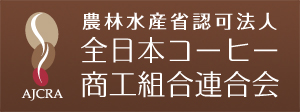2級講習会Q&A
次回は1級にて皆様にお会いできますのを楽しみにしております。
2級講習会にてご質問頂いた内容です。
総評
第45回秋コーヒーインストラクター2級検定試験総評
この度は第45回2級検定試験にご参加ありがとうございました。今回の試験では生産国から消費国まで幅広く出題いし、多くの方が合格結果となりました。
設問ごとまとめましたので、今後の学習の参考にしてください。
カップテスト[アラビカ種とカネフォラ種]…非常に高い正答率でした。基礎となる飲み比べを十分に理解されており技術が身についていました。
コーヒーの抽出について…全体的に高い正答率であり抽出の仕組みは十分に理解されています。ただし、一部で[成分による抽出速度の違い]や[モカポットとエスプレッソ抽出の違い]に間違いが見受けられました。
保存・インスタントコーヒー・リキッドコーヒーについて…焙煎豆の保存に関しては高い正答率でした 。一方で[冷凍保存したコーヒーを抽出する際の注意点][リキッドコーヒーの表示]に関してはより理解を深めていただく必要があります。
店頭販売における焙煎豆[焙煎・ブレンド]について…非常に高い正答率でした。焙煎およびブレンドに関しましては皆とてもよく理解されていました。販売現場でも自信をもって学んだ知識を活かしてください。
生産国の位置について…多くの方が点数を落とされており、合否を分けるポイントとなりました。生産国の位置関係や特定銘柄は、販売や商品選びにおいて非常に重要な要素です。代表的な生産国の位置や特定銘柄の定義はしっかりと覚えておきましょう。
コーヒーの種類、栽培や収穫、精選方法について…十分に理解されている方、点数を大きく落とされている方に分かれました。生産国に関する基礎知識になりますので、興味を持って取り組んでください。
格付けについて…全体的に理解されていますが、中米各国の等級名で迷われた方がいたように感じます。国ごとの格付け方法と等級名を正確に覚えることが今後のステップアップに繋がります。
全体を通してよく理解されていますが、生産国に関する問いが正答率が低い傾向にありました。生産国のことを正しく伝えることで消費国でのコーヒーに対する理解もより深まるはずです。
合格された方も、惜しくも届かなかった方も、今一度教本を見直し、コーヒーへの興味を深めていただければ幸いです。より多くの方と1級の講習会でお会いできることを楽しみにしております。
講習会でご質問いただいたQ&A
これより前半分野の質問です。
特定銘柄のクリスタルマウンテンの同国輸出規格の内容は何でしょうか
クリスタルマウンテンの産出国であるキューバでは、生豆の大きさによって等級分けが行われています。スクリーンサイズ(生豆の大きさ)が16以上はAL、17以上はTL、18以上はETLと分類。クリスタルマウンテンはETLよりも厳しい規格で選別されています。
特定銘柄のコロンビアスプレモの同国輸出規格は、格付けのエクセルソスプレモと同じでしょうか
同じです
エクセルソスプレモで一つのことばですか
エクセルソは輸出規格、スプレモは等級・グレードを表しています。
ペルーは水洗式が主なのに格付けが欠点でするのはなぜですか
昔は非水洗式が主流で、その頃の欠点の格付けが引き継がれているためだと思われます。
天日乾燥について、コンクリート床とアフリカンベッドのような高床で行う場合、時間や風味の優位性は異なりますか
コンクリート床と高床で乾燥時間は異なります。一般にコンクリートは蓄熱しやすく、地面に近いことで温度が上がりやすく乾燥が速い傾向、高床は風通しが良く、放熱により比較的ゆっくりになる傾向があります。風味の優位性としては、どちらが良い悪いということを言う事は出来ません。栽培、精選、選別全ての工程を通じた管理を徹底するほうが大切です。
過熟豆は欠点になるのでしょうか
代表的な過熟豆の形状というのはありませんので、教本P10の欠点豆のような形状をしていたら欠点豆になりますし、そうでなければ欠点豆にはなりません。
教本P23にはインドネシア(カネフォラ種)は非水洗式の箇所のみに記載、一方P25には非水洗式、水洗式両方の記載がある。どのように解釈したらよいか
表記は「代表的な精選方法」とご理解ください。インドネシアではカネフォラ種(ロブスタ)は、非水洗式・水洗式の双方が存在いたします。アラビカ種はスマトラ式が大半ですが、非水洗式や水洗式も一部で行われます。
特定銘柄について今後増える可能性はありますか
今後増える可能性は不明です。増えないと断言はできません。
生産量のスライド(教本P22)で説明して頂いたコロンビアの概要をもう一度説明お願いします。
コロンビアは生産量は世界第三位ですが、水洗式アラビカ種の生産量に限っていうと生産量世界一位の国となります。
ブラジルの格付けに関してもう一度説明お願いします。
ブラジルの格付けは欠点数に対して行われます。ただし一般的に多く流通しているものは、No.2はスクリーン17/18、No.4/5はスクリーン14/15/16というようにスクリーンも格付けに連動していますので、ここでは欠点数とスクリーンサイズによる格付けとしております。
スクリーンの違いによる味の差はあるのでしょうか。なぜ大粒の方が高値で取引される傾向があるのでしょうか。
結論から申し上げますと、スクリーンサイズ要因での品質差はありません。ただし、大粒の方が見栄えが良く消費者受けが良い場合が多いこと、生産量が少ない(やや希少である)場合が多いこと、などから、大粒の方が高値で取引される傾向があります。
4つの精選方法を教わりましたが産地では何を基準に選択しているのでしょうか
気候や地理的条件、また消費国側のニーズや生産国側のマーケティング戦略などによって決められています。
小規模農家と大規模農家で品質が安定しているのはどちらですか
農園単体で考えると農園の規模だけで優劣はつけられません。講義で説明した通り、大規模単一農園で作られたロットと小規模複数農家から作られたロットでは、大規模単一農園の方が土壌や精選設備において均一性が高くなる一方、小規模複数農園から作られたロットは様々な品質のものが混ざることがあり安定しない可能性があります。
Q.樹上乾燥させたコーヒーは通常の収穫タイミングではなくあえて樹上で乾燥させてから収穫することで風味を豊かにしたことを訴求している商品なのでしょうか?
A. はい、その通りです。樹上で乾燥させることで風味が豊かになると言われていますが、天候等による品質への影響に注意が必要で、完熟果実の状態で収穫することが一般的です。
欠点のカウント数についてもう一度教えてください。
国により異なりますが300g中の欠点数を測ることが一般的です。個数ではなく欠点豆の種類、重度によって1個で1欠点とするものがあれば10個で1点とする欠点もありその合計数が欠点数となります。ジャマイカのみ重量に対する割合となります。
特定銘柄のキリマンジャロについてなぜブコバ地区を除いているのか?
ブコバ地区はカネフォラ種の栽培エリアであることから除外をされております。
マンデリンの独特の風味はスマトラ式の精選処理によるものですか
精選方法によるものが大きいです。
各精選方法について、それを採用している国の共通点を教えてください。
非水洗式を採用している国の特徴としては収穫期が乾季に当たり、また乾燥に使用する広大な土地があることが挙げられます。一方水洗式を採用している国は頻繁に雨が降ることや山岳地など地理的な関係があり非水洗式には不向きであること、また早く乾燥させる必要があるという点で水洗式が採用されています。
欠点数はどの段階のものなのでしょうか?例えばG5のロットをたくさんハンドピックしてG1レベルにしたらG1として販売できるのでしょうか
輸出時のグレードがそのロットのグレードになるため輸入後ハンドピックをして欠点豆を減らしても高い等級のロットとしての販売はできません。
標高で格付けしているのは農園単位で登録されているのか、それとも地域単位で管理されているのか、どのようにSHBやHBの格付けがなされているのでしょうか
そのロットが栽培された標高で格付けが行われます。
昔はコーヒーを焙煎せずに煮汁を飲んでいた話を聞いたことがあるが、今もそのような飲み方をしている地域はあるのでしょうか
いまの知見では実際どの地域でどのように飲んでいたとかという情報はなく詳細は分かりません。
播種の際に生豆では発芽しないのでしょうか
生豆でも発芽すると思いますが、パーチメントコーヒーの方が発芽率が高く一般的になります。
インドネシアの格付けをもう一度教えてください。
格付けは欠点数に対して行われますが、カネフォラ種はそれとは別にスクリーンサイズによる格付けもあります。「グレード3・ラージ」「グレード3・スモール」のようになります。
格付けにおいて等級が高い(標高が高い・スクリーンサイズが大きい)方が価格が高いのでしょうか
標高が高い方が昼夜の寒暖差が大きいことにより品質が良くなる傾向にある事、また生産量が少ない事により標高が高い方が高値で取引されています。又、スクリーンサイズが大きい方が生産量が少ない事、大粒の方が見た目が良いなどの理由でスクリーンサイズが大きい方が高値で取引されています。
コロンビアではなぜスクリーンサイズのみで格付けを行っているのでしょうか
コロンビアでは基本的に標高が高い所でコーヒーが生産されている為に標高による格付けがされて無いと思われます。又、水洗式においては精選の過程で欠点豆が除去されやすく欠点が少なくなる傾向にあるため欠点による格付けが無いと思われます。
グアテマラなどの中米各国のアラビカ種はなぜ標高のみで格付けされているのでしょうか
中米各国では低地から高地まで様々な標高の場所でコーヒーを栽培しており、標高が高くなるほど昼夜の寒暖差の影響により品質が良くなりますので高地産の方が格付けは良くなります。低地産と比較すると高地産の方が小粒になる傾向がある為にスクリーンによる格付けが無いと思われます。又、水洗式の精選方法を採用している為に欠点が少なく欠点による格付けが無いと思われます。
市販されている商品名「タンザニア」のコーヒー豆は、キリマンジャロの定義で外れているブコバ地区産のコーヒーのことを意味するのですか
いいえ。そうではありません。ブコバ地区はカネフォラ種を多く生産されているキリマンジャロの定義からは外れていますが、タンザニアは生産国名となる為、ブコバ地区を含むタンザニアで生産されたコーヒー全てに表記する事ができます。キリマンジャロの定義に当てはまるコーヒーでも販売者の判断によりタンザニアと表記する事ができます。
収穫期において、赤道に近い地域にある「メイン」と「サブ」の違いは何ですか
比較的収穫量が多い時期をメイン、少ない時期をサブとしています。
生豆の欠点にある「発酵豆」「フローター」はどのようなものですか
「発酵豆」とは、精選過程で発生した欠点豆で意図としてない酸味や熟しすぎた果肉の風味などが感じられる欠点です。過熟、過発酵、地面との接触や乾燥不良等の様々な要因で発生します。生豆の「フローター」とは、見た目の色がうすく少しふやけたような外観をしており、水に浮く程度まで密度が軽くなった生豆です。原因は様々ですが主に乾燥工程や保管環境が不適切であったことによる乾燥不良が原因です。その他の欠点豆に関しては、マスター編になりますが、教本P114をご参照ください。
市販する場合でスペシャルティコーヒーを謳うための明確な基準はありますか
日本スペシャルティーコーヒー協会(SCAJ)が定義するもの(教本P27)がスペシャルティコーヒーとしての定義を満たすひとつの要因となりますが、消費国側でも統一した定義があるわけではありません。
スペシャルティコーヒーを謳うための基準がないとしたら、販売者が自己都合でスペシャルティを謳って良いでしょうか
スペシャルティーコーヒー定義を満たしていればそのように謳えます。消費者側にきとんと説明できる根拠は必要かと思います。
格付けにおいて、ブラジルやインドネシア(カネフォラ)のような、スクリーンと欠点の2つの基準を組み合わせる場合、販売者はその2つの基準を明記する必要がありますか
生豆を販売する場合には、使用者である焙煎業者が必要とする規格に沿った生豆供給を求められるケースが多いので、明記を求められることがほとんどです。又、 焙煎豆を小売する場合は、国名を表記するだけのケースが多く、付加価値がある規格(例えば大粒なブラジルNo.2 S-19など)以外は記載しないケースの方が多くみられます。
カネフォラ種の受粉において、他の樹の花粉を受粉させるために、人為的に受粉作業を行うことはあるのですか
基本的にありません。風や虫などの自然による要因である事がほとんどです
なぜブラジルのコーヒーの格付けは、「タイプ1」ではなく「タイプ2」が最高等級なのですか
ブラジルでは、「欠点豆が全く存在しないコーヒー(タイプ1)はあり得ない」という考え方に基づいているためです。必ず何らかの欠点豆は混入するという前提のもと、格付けが「タイプ2」から始まります。
同じ生産国の異なる銘柄を混ぜた場合、ブレンドと呼べますか
全日本コーヒー公正取引協議会の規約では、ブレンドコーヒーは「2か国以上の生産国のコーヒーを混ぜたもの」とされています。現在は、同一生産国の異なる2種類のコーヒーを混ぜたとしても「ブレンドコーヒー」とは表示できませんが、今後規約が緩和される可能性があるだろうとのお話も聞いております。
非水選式コーヒーの味や香りの特徴はどの様なものですか
生産国の栽培条件、種、品種、乾燥状況によっても変わりますが、柔らかな口当たりになる事が特徴です。
欠点の発酵豆が含まれると、カップの風味にどの様な影響がありますか
発酵豆が混入すると発酵したようなダメージのカップ傾向となります。
播種するためのパーチメントコーヒーは、未成熟果実、完熟果実、過熟果実のいずれの状態から得るのですか
一般的には完熟果実から得られます。
コロンビアのエメラルドマウンテンというコーヒーは特定銘柄に含まれないのですか
公正競争規約に示されている特定銘柄の例示には含まれていません。
欠点数について1袋あたりをカウントか、産地によってカウント方法が異なるのかどのようにカウントをしているのかを教えてください。
欠点数のカウント方法は国によって異なります。例えば、ブラジルやインドネシアは300gあたり、コロンビアは500gあたりなど国によって異なります。
続き)またそれは目視で行っているのか別の方法で行っているのかを教えてください。
カウント作業は1粒1粒を目視で確認しています。
欠点数のカウント方法を教えてください。また欠点は風味に影響を及ぼすのでしょうか
それぞれの欠点豆には国ごとにポイントが決められていて、それに準じて欠点数を算出します。例えば黒豆1粒で1欠点、欠け豆5粒で1欠点など国ごとに決められています。又、欠点豆は風味にも影響を及ぼし、異臭のリスクなどにもつながります。
欠点をハンドピックをしても元々の木の影響等で風味は変わらないのでしょうか
欠点をハンドピックしても栽培環境や管理方法によってベースとなる品質がありますのでハンドピックしたからと言って品質は良くなりますが風味が良くなるわけではありません。
ジャマイカではブルーマウンテンが高いイメージがあるが、ハイマウンテンに比べて品質は違うのでしょうか。また、No1やNo2との違いに対して上記特定銘柄の差はあるのでしょうか。
ジャマイカの格付けはスクリーンと欠点によりNo.1からセレクトに分類されます。その中でも収穫されたエリアが異なる商品としてブルーマウンテン地区かハイマウンテン地区かの違いになります。一般的に、ブルーマウンテンの方が認知度がある為、高くても購入する人が多いと思われます。
精選方法によって風味の優劣はありますか。
優劣は一概に言えませんが、風味の違いは生まれます。
ドライチェリーが欠点に入っているが、何故これが欠点なのでしょうか?
ドライチェリーは生豆ではないからです。正常な生豆とは異なるものが欠点となります。ドライチェリーが入っていると焙煎前に自分で脱殻する手間が増えますのでクレームの原因にもなり得ます。
ピーベリーとフラットビーンはどのように大きさを比べる、分けるのでしょうか。
二つを分けたいときには穴の形が違うふるいを組み合わせてわけます。一般的なふるい(スクリーン)の穴は円形をしており、この穴を通るかどうかでサイズを分けます。ピーベリーを分けたいときは楕円形の穴を組み合わせることで、平べったいフラットビーンは通り抜け、丸いピーベリーは落ちないようになります。
これより後半分野の質問をお答えします。
アフターミックスで複数種類の豆を全て同じL値で焙煎したものと、プレミックスでそれと同じL値で焙煎したものは同じ味になりますか。
同じ味にはなりません。L値は豆の外観色の指標です。プレミックスでは、硬さや水分量の異なる豆を同時に焙煎するため全体で同じL値であっても使用したそれぞれの豆毎ではL値に差も出ます。仮に、全て同じL値になったとしてもどのように焙煎したかによって、生成される成分などに差が出ます。
真空包装では酸素濃度を1%を下回るのは可能なのでしょうか
真空包装のみの場合、酸素濃度を1%を下回るのは難しいです。
「抽出」と「ろ過」の違いは何ですか
「抽出」は、コーヒーの「粉の成分」が、お湯(水)に移ること、「ろ過」は、そのコーヒーの「粉」と「抽出液(液体)」を、分離することです。ドリップの場合、「抽出」、「ろ過」が同時に進行するので、抽出時間の定義が難しい旨を説明いたしました。
ハンドドリップの「蒸らし」について、詳しく教えてください。
粉とお湯(水)が接触して抽出の始まりになります。粉体であり、コーヒーに含まれる油脂分の影響等でお湯が直ぐ粉に浸透しないので、親水性を高め、抽出を促すべく、「蒸らし」は重要なポイントになります。
教本P35の「粒度別にみた抽出時間と溶出量」のグラフは2つありますが、スライドではグラフは1つでした。何か違いはあるのでしょうか
P35のグラフの左側は収率を表しており、収率とは使用した原料のうち抽出液に移行した割合となります。P119に詳細はありますがマスター編で詳しく勉強していきます。教本では右側グラフの色素量(苦味成分)と酸味をあわせたイメージとなりまして、一方スライドでは先に色素量(苦味成分)のグラフをお見せして、その後酸味のグラフを別途お見せしています。P35の収率のグラフを色素量(苦味成分)、酸味で分け、1つのグラフにまとめているというイメージです。
浸漬法では教本P36のように酸味の抽出は速いとありますが、これはドリップでも当てはまるのでしょうか
はい、ドリップでも同じように酸味の抽出は速い結果になります。抽出の出始めのコーヒー液だけを飲んでみると、より違いが分かるかもしれません。
スライドのまとめの表でドリップでは粉の量に対して「時間に影響」と書かれ、浸漬・サイフォンには「-」と表記されていました。これは何か意味があるのでしょうか
浸漬・サイフォンはドリップと違い、抽出とろ過が別々に起こり抽出時間と湯と粉の接触時間が同じと見なせるため、粉の量によって時間の影響は受けません。影響を受けないという意味で「-」という表記にしています。
ドリップの1人前と2人前では湯と粉の比率が同じ場合、時間の影響により濃くなることが分かりました。もしこれを同じような味わいにするためにはどのような工夫が必要でしょうか
一例ではありますが、2人前の際に粉量を少し減らす手法があります。しかし同じような濃度になっても、成分のバランスが変わってしまう可能性もございます。他にも抽出時間をなるべく減らすような投入方法にするなども考えられますがいずれも試行錯誤が必要です。ぜひチャレンジしていただいて見つけだしていただけたらと思います。
水出しコーヒーのグラフについて、もう一度教えてください。
水出しコーヒーは、抽出にお湯では無く水を使用します。水に溶け難い成分の抽出量が少なくなり、湯を使った抽出とは違った味わいのコーヒーになります。
ブラックコーヒーで甘さを感じることがあります。何が由来となって甘さを感じるのですか
残念ながら甘さの由来となる成分はまだ解明されておらず、分かりません
インスタントコーヒーの製造で、揮散した香気成分を回収して再付加する手法が近年みられると、教本に記載されていますが、これはフリーズドライ、スプレードライどちらにも行われているのですか
両方でおこなわれております。
水出しコーヒーはカフェインが少ない、または入っていないというのは本当ですか
同じ粉量・湯量・挽き目が同条件の場合、抽出温度が低い水出しコーヒーは、熱湯抽出より一般的にカフェインの抽出量がやや少なくなる傾向があります。ただし、水出し抽出は一般的に細挽きの粉を使用することや抽出時間を長くするため、低温でもカフェインが徐々に溶出し、高温抽出との差が縮まる、あるいは近い抽出量になる場合もあります。
レギュラーコーヒーとは何ですか
レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約では、レギュラーコーヒーとは、「コーヒーノキの種実を精製したコーヒー生豆(以 下「コーヒー生豆」という。)を焙煎したもの(以 下「煎り豆」という。)及び煎り豆にコーヒー生 豆を加えたもの並びにこれらを挽いたものをいう。」と定義されています。
焙煎豆の劣化に関して、焙煎直後にでるガスによって劣化はするのでしょうか。
焙煎直後は豆の内部から炭酸ガスが放出されている為、酸素と接触することでの劣化は起きにくい状況です。
抽出方法の浸漬に関して検定では「しんし」と読んでいますが「しんせき」と読むことをよく見かけます。同じ意味なのでしょうか。
液体にひたす意味であることから同じと考えて頂いて構いません。
抽出に関して「蒸らし」の工程は、教本P33の粉内部から外への移動にあたるのでしょうか。 もしくはどの工程になるのでしょうか。
当検定では蒸らしについては定義をしておりませんが、抽出時間の一部だと考えてください。蒸らしを行えば抽出時間が長くなるので抽出液は濃くなり、行わなければ抽出時間が短くなるので抽出液は薄くなります。
教本P35記載の粒度に関して800μや600μは市販で販売している細引き、中挽きなどどのていどの粒度に該当するのでしょうか。
中挽き程度と考えてください。ただし実際に市販されているものは、その粒度を中心に大きい粒度から小さい粒度のものが混ざった状態となっております。
水質がコーヒーに与える影響について教えてください。
硬水を使用すると弱酸性であるコーヒーと中和し、よりマイルドな味わいになります。軟水の場合にはそれが発生しません。
包装方法についての講習で、鮮度の高い豆であれば、ガスバリア性の低い包装でも短期間、経時変化を抑える事ができると説明がありました。具体的にはどれ位の期間でしょうか。
具体的な期間の明示は難しいです。生豆の種類や焙煎方法、焙煎度合いによって炭酸ガスの放出量が変わってしまうことや、保管環境によっても放出スピードが変わってしまう為です。
普段、手挽きミルを使っていますが、挽く時に粉が舞ってしまうのを防ぐために、いつも霧吹きの水でコーヒーを湿らせています。これはコーヒーの品質に悪影響でしょうか。
挽いた粉をすぐに抽出で使用するのであれば、問題ないと思われます。但し、その粉を保存するのであれば、湿ったことで経時変化に影響が出るかもしれません。また、ミルも濡れてしまうので、適切な清掃を実施しないと、異臭が発生するおそれもありますので、注意が必要です。